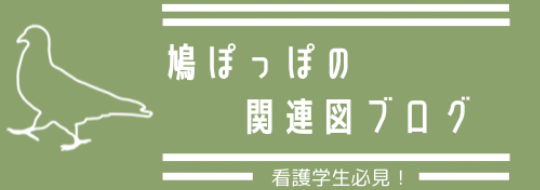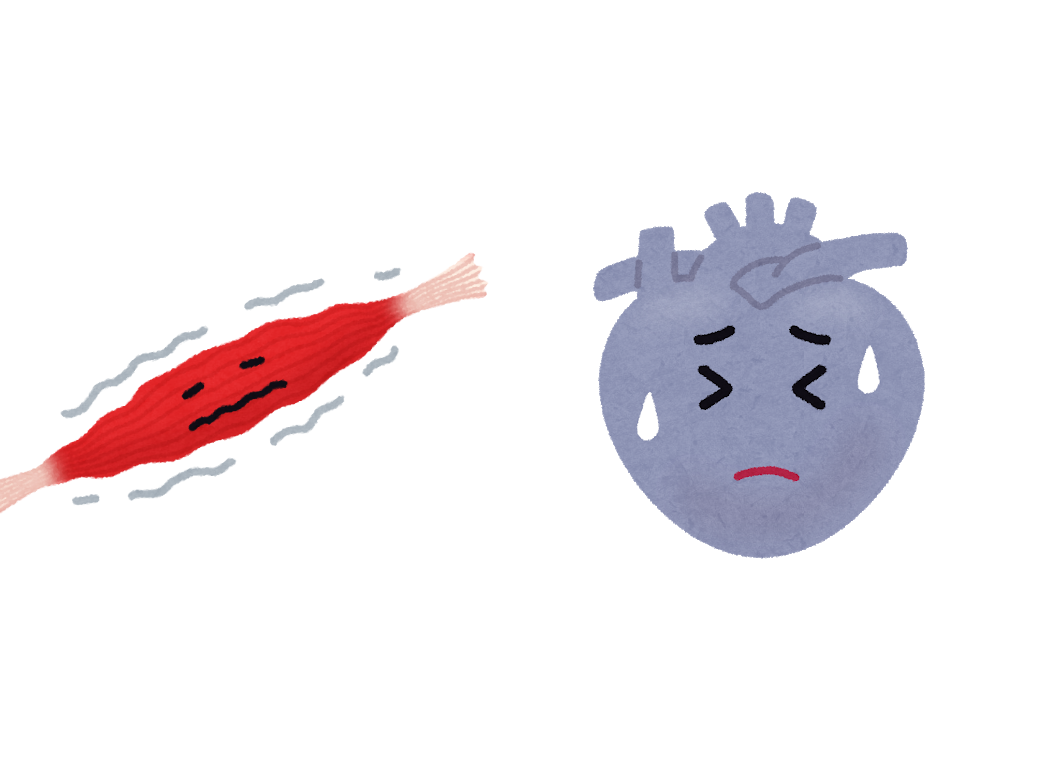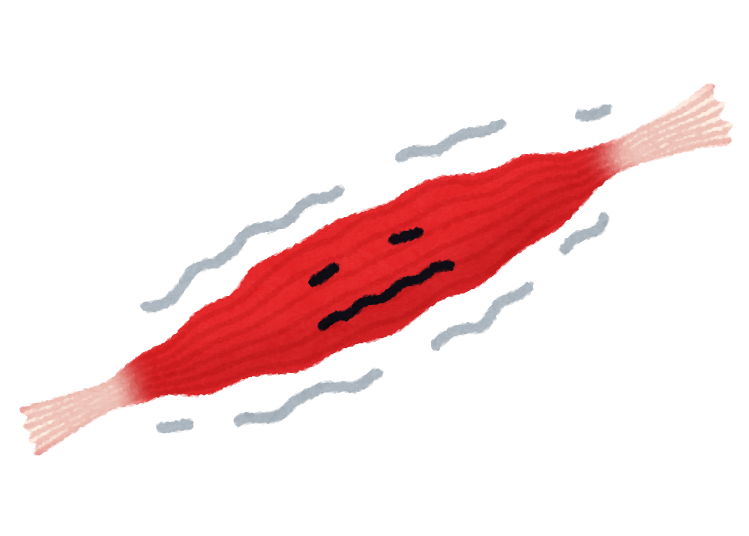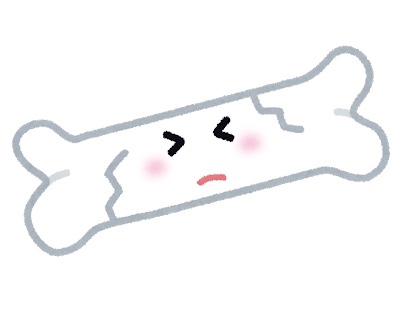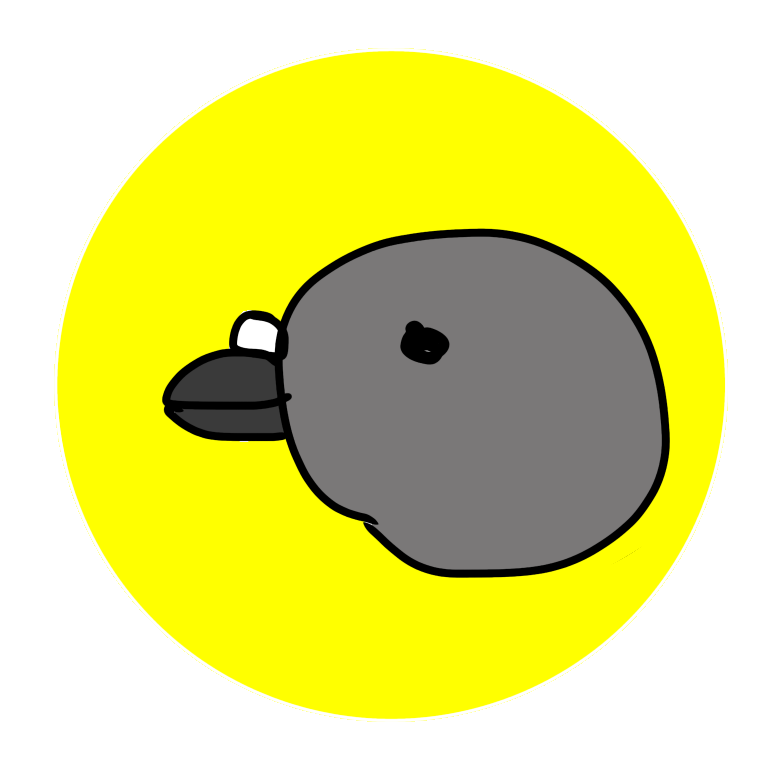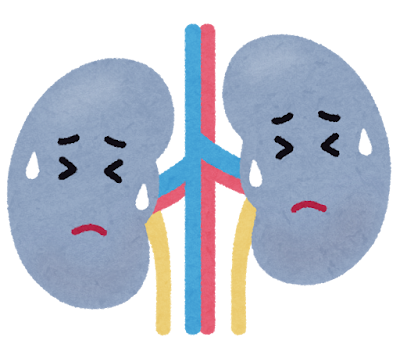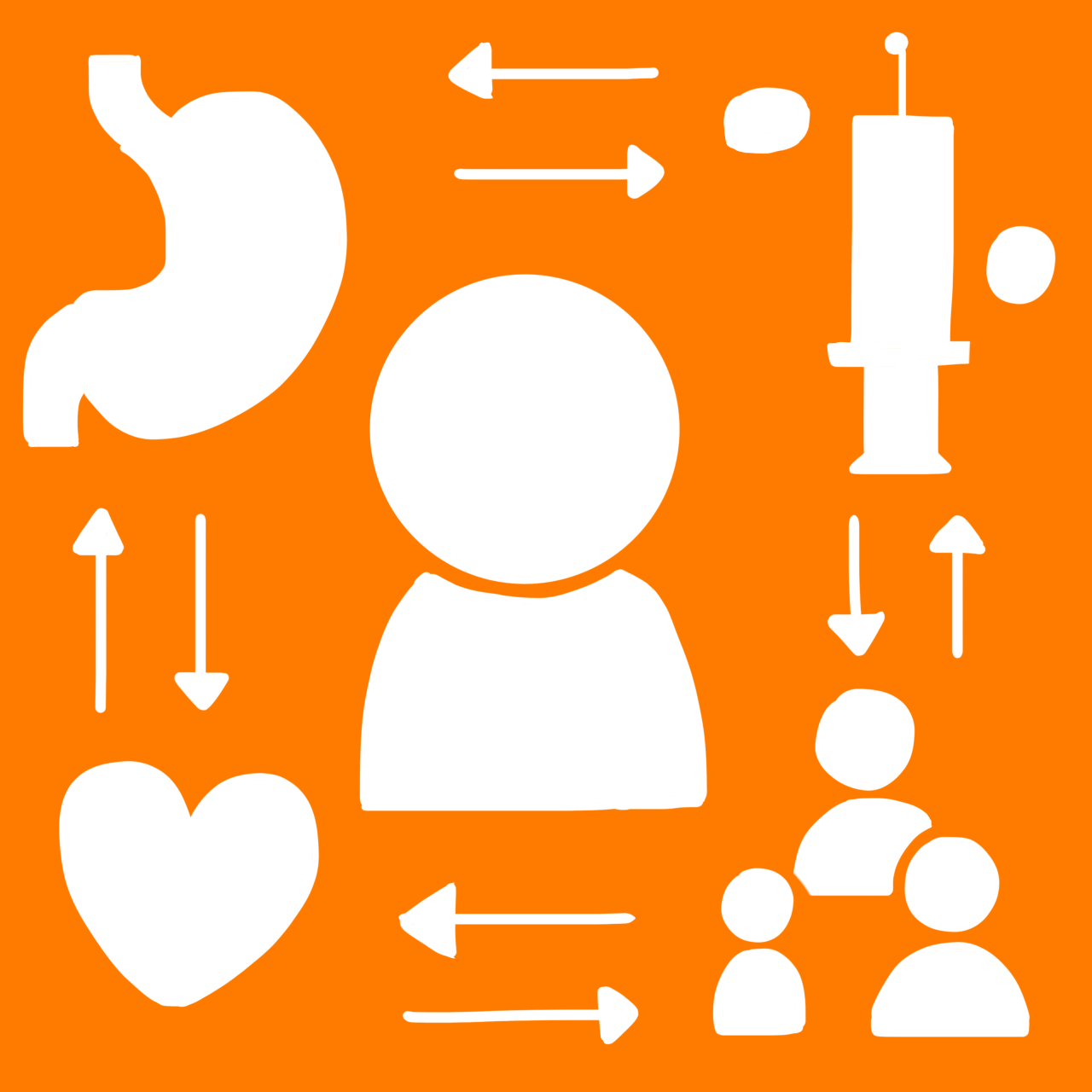男性産業保健師の鳩ぽっぽです。
今回の関連図は重症筋無力症です。
この記事で知れること
- 看護学生レベルで知っておいた方がいい病態情報
- 本疾患でよく出る看護診断、看護問題
- 本関連図の特徴や押さえておいた方がいい知識
病態
重症筋無力症(Myasthenia Gravis, MG)は、神経と筋肉の接合部(神経筋接合部)で、神経から筋肉への情報伝達がうまくできなくなる自己免疫疾患です。
通常、神経からアセチルコリンという神経伝達物質が放出され、筋肉にあるアセチルコリン受容体と結合することで筋肉が収縮します。
しかし、重症筋無力症では、このアセチルコリン受容体に対する自己抗体が産生され、受容体が破壊されたり、機能が阻害されたりします。これにより、神経からの指令が筋肉に伝わりにくくなり、筋力の低下や易疲労性を引き起こします。
重症筋無力症の症状は、時間帯や反復運動によって変動する「日内変動」と「易疲労性」が特徴です。
朝は元気でも、夕方になると症状が悪化したり、同じ動作を繰り返すことで筋力が低下したりします。
症状が現れる部位によって、以下のように分類されます。
- 眼筋型:眼瞼下垂(まぶたが下がる)、複視(ものが二重に見える)など、目の筋肉の症状が主です。
- 全身型:四肢の筋力低下、嚥下障害(飲み込みにくい)、構音障害(話しにくい)など、全身の筋肉に症状が現れます。特に、呼吸筋が麻痺するクリーゼは命に関わる重篤な状態です。
看護問題・看護診断
- ガス交換障害
- 嚥下障害
- 活動耐性低下
- 不安
最も注意すべきなのは、呼吸筋の麻痺によるガス交換障害です。呼吸困難やSpO2の低下など、呼吸状態の観察は最重要となります。また、嚥下障害によって誤嚥性肺炎のリスクが高まるため、食事の形態や摂取時の姿勢にも配慮が必要です。
日内変動と易疲労性があるため、患者さんの筋力に合わせた活動計画を立てる必要があり、活動耐性低下も重要な看護問題です。
慢性的な疾患であり、症状の変動や将来への不安も看護の重要な側面となります。
ポイント
重症筋無力症の関連図を作成する際は、「アセチルコリンとアセチルコリン受容体の関係」「自己抗体による神経伝達の阻害」という根本的な病態を理解することが不可欠です。
ここから「筋力低下」という共通の症状につながり、それがどの部位に現れるか(眼瞼下垂、嚥下障害、呼吸筋麻痺など)を具体的に書くと良いでしょう。
また、筋力の変動が著しいため、朝と夕方で症状が異なること、治療によって症状が改善すること、過活動によって症状が悪化することなど、動的な病態として捉えることがポイントです。
特にクリーゼは緊急性が高いため、その兆候と対応についてもしっかりと関連図に含めるようにしましょう。
重症筋無力症の病態関連図
重症筋無力症の病態関連図↓
参考引用文献
MSDマニュアル家庭版.重症筋無力症
南山堂.看護のための臨床病態学改訂4版.重症筋無力症p480
医学書院.看護診断ハンドブック第10版
医学書院.疾患別看護過程第2版
関連リンク
病態関連図記事はこちら→鳩ぽっぽの関連図ブログ病態関連図の販売一覧はこちら→鳩ぽっぽの関連図ストア
看護学生、編入、産業保健のお役立ち情報はこちら→鳩ぽっぽのnote
鳩ぽっぽのYouTubeチャンネルはこちら→鳩ぽっぽのYouTubeチャンネル
Twitterはこちら→鳩ぽっぽのTwitter